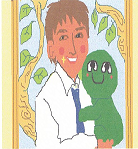“神社検定”って知ってる?
という記事で“第3回・神社検定”なるマニアックな検定の記事を書いたのは
2014年の11月
■“神社検定”って知ってる?
あの時は参(3)級を受験して合格
■神社検定の商売根性がスゴイ!
って記事でも宣言したように
参級以上はマニアックすぎる内容なので、絶対に受験しないつもりでいたのに
色々と事情がありまして
第6回・神社検定の弐(2)級を受験することになりました・・・
 ひとまず弐級の出題範囲である公式テキスト2冊と
ひとまず弐級の出題範囲である公式テキスト2冊と
まじめに前年の過去問を1冊購入
「神社のいろは・続」1749円
「神話のおへそ“古語拾遺”編」2160円
「第5回神社検定 問題と解説」1296円
これに検定料5900円を足したら・・・
合計11105円!!!
恐るべし検定ビジネス・・・
 試験は6月18日に行われました
試験は6月18日に行われました
4月から6月は専門学校の授業もあったし
春になってバス釣りシーズンの到来でしょ
試験勉強をする時間がなかなかとれなくて自信はなかったんですが
なんとか無事に合格することができました♪
 100点満点中、70点以上で合格
100点満点中、70点以上で合格
自分の点数は77点でした
平均点は64.2点で
合格率は39%だったようです
第4回の弐級の合格率が17.3%だったことを思えば、かなり難易度は下がったみたいですね
先日の南東北ツアーでご一緒したバスガイドさんに神社検定の話しをしたら
「あ、じゃあオスメスのシンボルが付いてる狛犬がある神社が日本に3ヶ所あるらしいけど、そーゆー問題出るの?」
って聞かれた・・・
いやいやそんな下ネタ出ませんから!!(笑)
でもそーいう問題の方が神社に親しみが持てていいかもしれませんね
神社検定弐級の出題範囲は、この先の人生で絶対使わないような知識ばかりでしたから・・・
ちなみに先日ブログでも紹介した吉田神社に関する問題もしっかり出ていたので最後に載せておきますね
■吉田神社に行ってきました♪
吉田兼倶のことについて書かれた以下の文章を読んで◆問27から◆32までの設問に答えてください。
祀官側からの神道説として提唱された伊勢神道は、吉田神道へとつながっていきます。
吉田家の本姓は卜部で、その後、古典の研究をもって家職とするようにもなり、
卜部兼方が編んだ『日本書紀』の注釈書である(ア)はその代表的な著述です。
兼倶は応仁元年(1467)に神祇権大副となりますが、応仁の乱が勃発します。
この時期においても、兼倶は幾人かの弟子に神道伝授を行っています。
文明8年(1476)には、神祇伯を世襲した家柄である(イ)に対抗して「神祇管長上」などと称しました。
兼倶は吉田神社近くの吉田山上に、日野富子の援助を受けて「太元宮」を建立します。
太元宮には主神である太元尊神(ウ)と天神地祇八百万の神が祀られています。
(ウ)は『日本書紀』(本文)で天地開闢のときに最初に現れた神様です。
自らの神道説を兼倶は(エ)などと呼びました。
また(オ)も主張しました。
仏教が日本で広まるのは、その根本である日本に帰ることだと理解していたからです。
兼倶は(カ)と(キ)も発行し始めます。
これが吉田神道説を全国に広め、権威となっていく契機になりました。
=実際の試験では(ア)から(キ)に入る語句を4択で選びます=
(ア)釈日本紀
(イ)白川家
(ウ)国常立尊
(エ)六根清浄神道
(オ)根本枝葉果実説
(カ)宗源宣旨
(キ)神道裁許状
という記事で“第3回・神社検定”なるマニアックな検定の記事を書いたのは
2014年の11月
■“神社検定”って知ってる?
あの時は参(3)級を受験して合格
■神社検定の商売根性がスゴイ!
って記事でも宣言したように
参級以上はマニアックすぎる内容なので、絶対に受験しないつもりでいたのに
色々と事情がありまして
第6回・神社検定の弐(2)級を受験することになりました・・・
 ひとまず弐級の出題範囲である公式テキスト2冊と
ひとまず弐級の出題範囲である公式テキスト2冊とまじめに前年の過去問を1冊購入
「神社のいろは・続」1749円
「神話のおへそ“古語拾遺”編」2160円
「第5回神社検定 問題と解説」1296円
これに検定料5900円を足したら・・・
合計11105円!!!
恐るべし検定ビジネス・・・
 試験は6月18日に行われました
試験は6月18日に行われました4月から6月は専門学校の授業もあったし
春になってバス釣りシーズンの到来でしょ
試験勉強をする時間がなかなかとれなくて自信はなかったんですが
なんとか無事に合格することができました♪
 100点満点中、70点以上で合格
100点満点中、70点以上で合格自分の点数は77点でした
平均点は64.2点で
合格率は39%だったようです
第4回の弐級の合格率が17.3%だったことを思えば、かなり難易度は下がったみたいですね
先日の南東北ツアーでご一緒したバスガイドさんに神社検定の話しをしたら
「あ、じゃあオスメスのシンボルが付いてる狛犬がある神社が日本に3ヶ所あるらしいけど、そーゆー問題出るの?」
って聞かれた・・・
いやいやそんな下ネタ出ませんから!!(笑)
でもそーいう問題の方が神社に親しみが持てていいかもしれませんね
神社検定弐級の出題範囲は、この先の人生で絶対使わないような知識ばかりでしたから・・・
ちなみに先日ブログでも紹介した吉田神社に関する問題もしっかり出ていたので最後に載せておきますね
■吉田神社に行ってきました♪
吉田兼倶のことについて書かれた以下の文章を読んで◆問27から◆32までの設問に答えてください。
祀官側からの神道説として提唱された伊勢神道は、吉田神道へとつながっていきます。
吉田家の本姓は卜部で、その後、古典の研究をもって家職とするようにもなり、
卜部兼方が編んだ『日本書紀』の注釈書である(ア)はその代表的な著述です。
兼倶は応仁元年(1467)に神祇権大副となりますが、応仁の乱が勃発します。
この時期においても、兼倶は幾人かの弟子に神道伝授を行っています。
文明8年(1476)には、神祇伯を世襲した家柄である(イ)に対抗して「神祇管長上」などと称しました。
兼倶は吉田神社近くの吉田山上に、日野富子の援助を受けて「太元宮」を建立します。
太元宮には主神である太元尊神(ウ)と天神地祇八百万の神が祀られています。
(ウ)は『日本書紀』(本文)で天地開闢のときに最初に現れた神様です。
自らの神道説を兼倶は(エ)などと呼びました。
また(オ)も主張しました。
仏教が日本で広まるのは、その根本である日本に帰ることだと理解していたからです。
兼倶は(カ)と(キ)も発行し始めます。
これが吉田神道説を全国に広め、権威となっていく契機になりました。
=実際の試験では(ア)から(キ)に入る語句を4択で選びます=
(ア)釈日本紀
(イ)白川家
(ウ)国常立尊
(エ)六根清浄神道
(オ)根本枝葉果実説
(カ)宗源宣旨
(キ)神道裁許状